こんにちは、manabi-mamaです。
「うちの子、ぜんぜん勉強しない…」
ゲームやスマホばかりで、声をかけても「あとでやる」と返される毎日。
そんな中2男子と家庭学習を選んだ我が家も、最初は同じように悩んでいました。
それでも、親子で向き合いながら試行錯誤を重ね、今では「1日2時間の勉強」がようやく少しずつ習慣に。
この記事では、勉強が続かなかった息子が、どうやって「1日2時間の家庭学習」を習慣にできるようになったのか、我が家で実践した 5つの工夫をご紹介します。
「どうしたらうちの子も…?」と悩む方のヒントになればうれしいです。
工夫① 塾に行きたくない息子と始めた家庭学習
中学1年の春、息子に「勉強どうする?塾行く?」と聞いたとき、返ってきたのは一言。
「塾は絶対に行きたくない。」
え?それで本当に大丈夫なの…?
正直、不安でいっぱいでした。でも、「自分で勉強する」という覚悟があるなら、まずは信じてみよう。塾に通うのは、どうしても必要になったときにすればいい。
「塾に行かないなら、自分でやるしかないよ?
やるって言ったからには、ちゃんとやってね。」
そんな風に話して、我が家の家庭学習がスタートしました。
……とはいえ、最初から順調にいくわけもなく。
ゲーム、スマホ、ダラダラ…。まさに“やらない理由”のオンパレード。
毎日声をかけても、つれない返事ばかり。
それでも、「やるって決めたのは本人だから」と、ぐっとこらえて見守りながら、
まずは英語と数学を1ページずつ進めることからスタート。
ほんの少しずつですが、“勉強する時間”を生活の中に組み込んでいきました。
工夫② 最初に決めたのは「時間」だけ
勉強する時間を決めた(夜8:30〜スタート)
家庭学習を始めたばかりの頃、とりあえずテキストは用意したものの、正直何がいいかわかりませんでした。
でも、まずは「とにかく机に向かう時間をつくること」から始めてみようと進めてみました。
入学直後、息子と一緒に話し合って、夜の勉強時間を決めました。
ゲームやスマホからなかなか離れられないからこそ、毎日決まった時間に「勉強する」ことを習慣にしようと考えました。
最初は1日1時間でもいい。
英語と数学のテキストを1ページだけでもいいから取り組む。早く終わればそれでよし。それがスタートでした。内容よりも「時間」を優先。
リズムが整えば、あとから勉強の中身も変わっていく。そう信じて、毎日同じ時間に声をかけるところから始めました。
無理はさせない、でもブレないルール
毎日2教科・1日2時間の家庭学習——
これが理想ではありますが、
日によっては宿題が多かったり、疲れていたりして、予定通りにいかない日ももちろんあります。
そんな日は、無理せず柔軟に対応しています。
我が家のルールは「続けることが大事」!
- 📝 学校の課題がある日は、それを優先
- ✏️ 2教科が難しい日は、1教科だけでもOK
- 📘 問題が多すぎて手がつかない日は、半分だけ解く
- 😴 疲れている日は“お休み”してもいい
どんなに少なくてもいいから、
「今日は何もやらなかった」という日をできるだけつくらない。
これが、我が家の “ブレないルール” です。
「できなかった」ではなく、
「ちょっとでもできた」と感じられるように。
無理はさせず、でも続ける。
そんな家庭学習を目指しています。
工夫③ 勉強内容はシンプルに基礎重視
やっぱり大事なのは “基礎の土台”
家庭学習を始めたばかりの頃、
私は正直——ちょっと勘違いしていました。
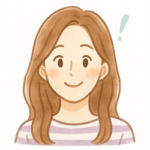
発展問題集をやれば、実力がつくんじゃないか?
そんなふうに思い込んでいたんです。
でも実際は…
- 基礎があいまいなままだと、
応用問題に太刀打ちできない! - 解き方自体がわからない → 手が止まる → 集中力が切れる
息子は割と覚えが早い方かな、と思っていたので、学校で基礎を学んでくれば、家では応用問題だけですみそうな、そんな気がしていましたが、めちゃくちゃ甘かったです。
そこで思い切って「基礎重視」に方針転換!
今はとにかく“基礎の定着”を重視しています。
- ✂️ 使う教材を絞る
- 📘 「これ1冊」をやり切るシンプルなスタイルに
- 💪 「できた!」の小さな達成を積み重ねる
定着してきたかな、と感じたら、発展・応用へチャレンジする!といった流れにしています。
「迷わない仕組み」で、毎日の勉強をラクに
勉強を習慣にするうえで、意外と負担になるのが「今日は何をやろう?」という“迷い”です。
我が家では、その迷いを減らすために、中1のはじめは 「英語1ページ+数学1ページ」 を毎日の基本ルールにしました。
量としては少なめで、だいたい1時間かからないくらい。でも、最初は“続けること”が何より大切だと思ったからです。
このやり方は、お子さんの性格や生活スタイルに合わせて、自由に変えてOKだと思っています。
曜日ごとに教科を固定してもいいですし、週末は復習の日にしてもいいかもしれません。
「これなら、自分にもできそう!」
そう思えるスタイルを、一緒に探していくことが、習慣化のいちばんのコツだと感じています。
工夫④ 親の関わり方は“伴走者”が正解
声かけは「監視」ではなく「伴走者」に
家庭学習を始めた頃、私は「わからないことがあったら聞いてね」とだけ伝えて、
自分で解いていくスタイルにし、なるべく口出ししないようにしていました。
でも、なかなか勉強が進まない。
特に難しい問題に差しかかると、集中力が切れて手が止まってしまうこともしばしば。
そんなときは、一緒に問題を考えたり、解いたり。
あるとき、一緒に解いている時の息子の表情を見て、明るくなったように感じました。
「親と一緒に考える」ことで、
“やらされている勉強”が、“前向きに取り組む勉強”に変わっていたのかもしれません。
一人でやらせるのが自立だと思っていたけれど、
そばで一緒に悩んで、考えてあげることも、立派なサポートなんだと気づきました。
今では、私も一緒に解きながら、
「ここは間違えやすいかも」とか「これはよく出るね」など、
会話を少し挟むようにしています。
勉強時間は、ただの“作業”ではなく、
親子で“前に進む時間”に変わってきました。
一人でやるよりも、誰か仲間がいるほうがいいこともあります。
勉強中のちょっとした“達成感”を共有
家庭学習をしていると、小さな成長の瞬間に出会えます。
昨日は解けなかった問題が、今日はできたとき——
「すごい!できるようになったね」
そんな言葉をかけると、子どもはちょっぴり誇らしそうな顔を見せてくれます。
逆に、私自身がわからない問題に出くわすこともあります。意外とそれがおもしろかったりします。
「これ、どうやるの?ちょっと教えてくれる?」と子どもに聞くと、うれしそうに説明してくれることも。
私も完璧ではないし、間違えることもある。苦手なところもたくさんあります。
そういう姿を隠さずに見せることで、「大人だって学び続けているんだな」と伝わる気がします。
一方的に“教える・管理する”のではなく、親子で学び合うスタンス。
その積み重ねが、信頼とやる気を育てているのかもしれません。
工夫⑤ 続かない日との付き合い方
「1日2時間の家庭学習」
なんて書くと、スムーズに続いているように聞こえるかもしれませんが、そんなことはまったくありません(笑)。2時間の家庭学習ができるようになるまで半年以上時間がかかっています。
スマホやゲームがキリのいいところで終わらず、予定の時間を1時間過ぎる…なんてことはしょっちゅうです。
「今日はやる気が出ない」「明日やるから」など、やらない理由はいくらでも出てきます。
ときには不貞腐れて何を言ってもだめなことも。私も何度もキレたことか。
それでも私が大切にしているのは、「自分で決めたことは、自分で守る」という姿勢です。
うちでは、できる限り子ども自身に決めてもらっています。選択肢は一緒に考えます。
最後に決めるのは子どもで、その決断に私は何も言わないと決めています。
決めたからにはやる。“有言実行”。
もちろん、どうしてもできない日があってもいいと思っています。
でも、基本のスタンスとして「自分の言葉と行動に責任を持つ」
それは、社会に出ていく中でも大事なことだと思っています。
親としては「厳しいかな?」と思う時もありますが、自分で決めたことをやり遂げる力をつけてほしいという思いを込めています。
まとめ:家庭学習は、少しずつ“育てる”もの
最初からうまくいくなんて、ほとんどありません。
うまくいかない日もあるし、反抗期の中学生相手に「もう塾行ってくれた方がラク…」と思うことも、正直たくさんあります。とはいえ、塾に行ったからといって成績が確実に上がるわけではないのも事実です。
そんな日々でも少しずつ、ほんの少しずつ続けていくうちに、子どもも親も少しずつ変わってきます。
「家庭学習でどこまで成績が上がるか」ではなく、
「毎日の積み重ねが、どんな力になるか」を信じて進んでいるところです。
塾に通えば、解く問題量も、勉強時間も、まったく違います。
特に中3にもなれば、その差はどんどん大きくなっていく。
だからこそ、塾に通っていない“今”の時間を活かす。時間を有効に使う。
今のうちにしっかり基礎を積み上げて、「自分で学ぶ力」を育てていくことを目指しています。
それは、息子の性格やペースを見たうえで決めた、わが家なりの選択です。
家庭学習も、まるで植物を育てるように、時間をかけて育てていくもの。
焦らず、あきらめず、これからも少しずつ積み重ねていきたいと思います。
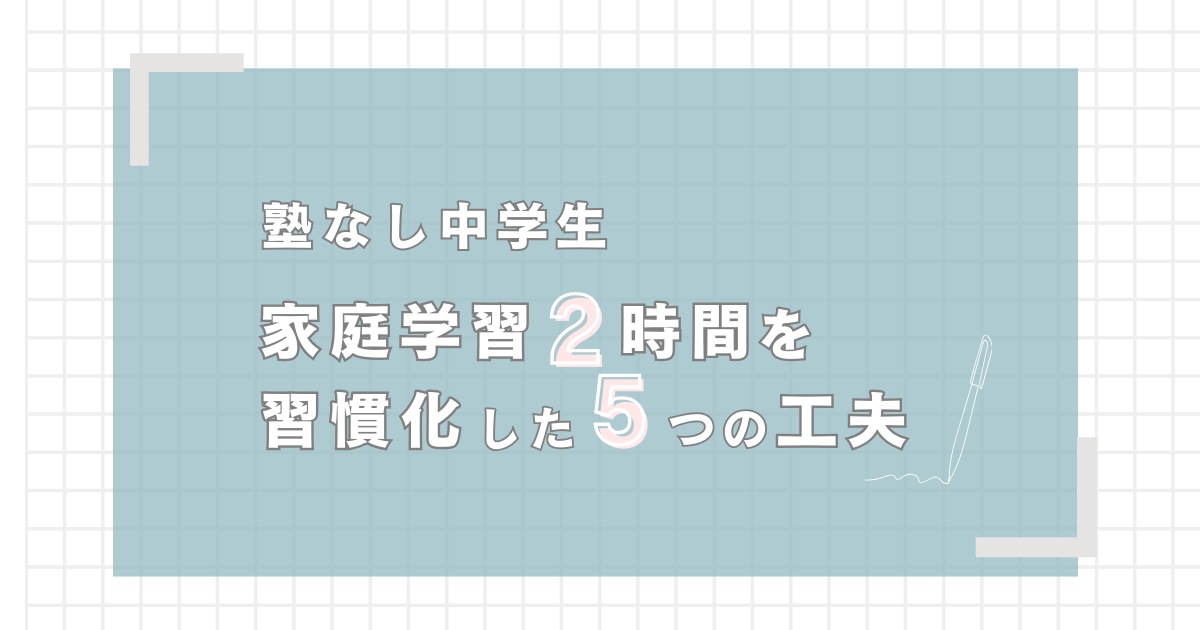
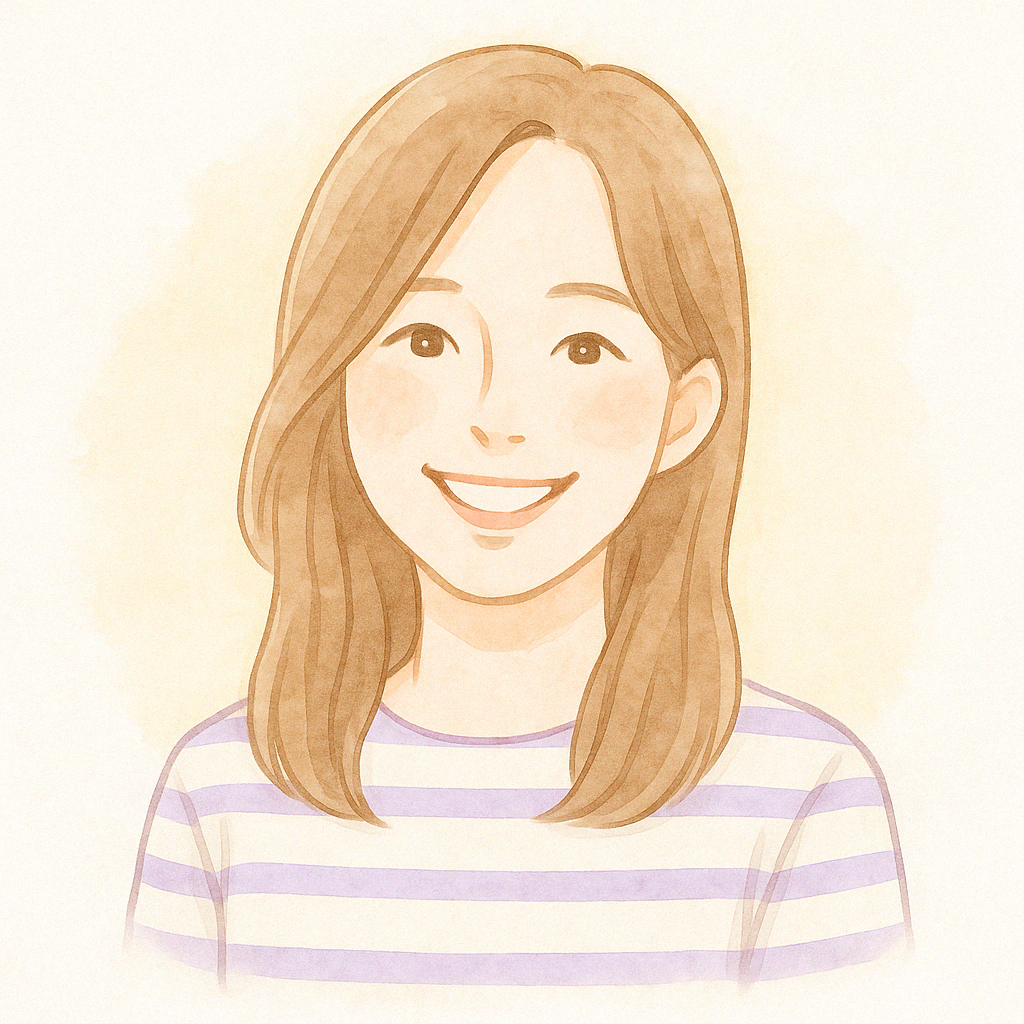
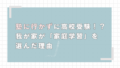
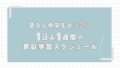
コメント